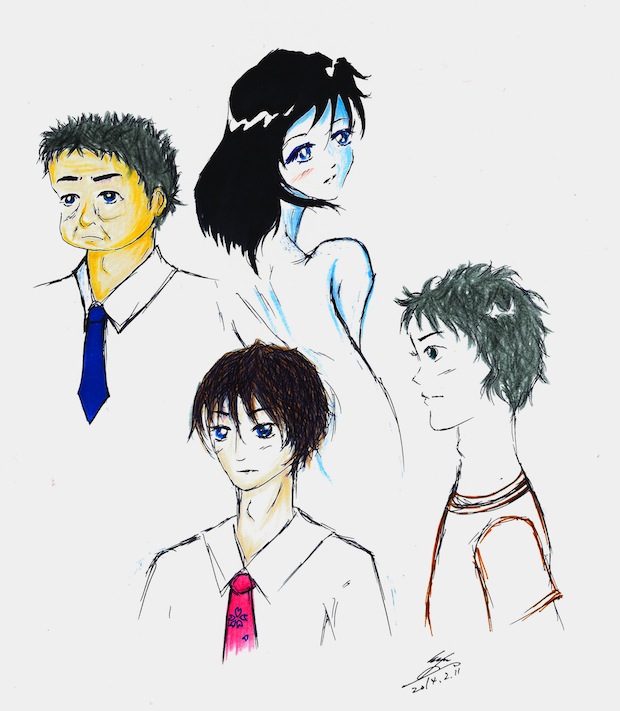【前回までのあらすじ】雨の日、バイト帰りの普通の女子大生 静眼(しずめ)についナンパしてしまった刑事 勝也。二人は流れるように惹かれ合い一夜限りの逢瀬を過ごす。翌日の朝、静眼は自分の彼氏の不審な行動を勝也に打ち明け、不安を共有した。そうこうしているうちに二人は駅の改札で別れ、また二人はそれぞれの自分の日常に戻っていくのだった。
【前回までのあらすじ】雨の日、バイト帰りの普通の女子大生 静眼(しずめ)についナンパしてしまった刑事 勝也。二人は流れるように惹かれ合い一夜限りの逢瀬を過ごす。翌日の朝、静眼は自分の彼氏の不審な行動を勝也に打ち明け、不安を共有した。そうこうしているうちに二人は駅の改札で別れ、また二人はそれぞれの自分の日常に戻っていくのだった。
またいつかどころではなかった。
「静眼ちゃん?」勝也は動揺せずにはいられなかった。
「・・・」ヒック、ヒック、というしゃくり上げた声だけが受話器から聴こえてくる。
「勝也さん、どうしよう・・・。110番・・・だよね・・・普通・・・。」しゃくり上げながら必死に静眼は話す。
勝也はすぐに署を抜けて現場に向かった。まずは自分が状況を見ようと思った。
静眼の言っていた事は確かに本当だった。
静眼の彼氏の死体が、彼の家の玄関で残忍な置かれ方をしていた。
血だらけで、傷だらけで、目は大きく見開いて死んでいた。
静眼が動揺し号泣しないはずがない、光景だった。
「・・・110番だね。」勝也はこういう時はさすがに冷静だ。
・・・コクン、と静眼は頷いた。
「明らかに他殺だよなあ。」刑事の星野さんは眉間に皺を寄せた。
「そうですね。」勝也は先輩の星野さんに敬意を示しながら答える。
「第一発見者は。」
勝也はチラっと静眼に目をやった。
星野は静眼に近づいた。
「刑事の星野です。少し、お話を伺いたいので、署までご同行願いますか?」警察手帳を開きながらやんわりと言った。
「・・・はい。」少し鼻をすすって、静眼は答えた。目はすっかりうさぎのように真っ赤だ。
「僕も一緒に行きます。」勝也はずいと出た。
「お前は現場でちゃんと調べ上げろ。」星野が強く返した。
「勝也さん。私は大丈夫。」静眼は勝也を見上げてニコっとした。
「なんだ?2人は知り合いか?」星野がきょとんとした。
「あ、はい。まあ。知り合いというかなんというか。」
「それなら、お前も来い。その方が彼女も気が休まるだろう。第一発見者は容疑者になり得るとはいえ、トラウマになるようなもん見ちまったんだからな。一応彼女も被害者だ。お前も一緒にいてやったらいい。」ベテランの香りに満ちた洞察と発言で、現場はピリっと引き締まった。
「あ、はい。ありがとうございます。」勝也は、少し喜んだ。好きな子のそばにいられるのは、どんな状況でも本能的に嬉しくなってしまう。
どう考えても、明らかに静眼に犯行の可能性は0に限りなく近かった。
静眼にはアリバイがあった。死亡推定時刻の時間帯はちょうどバイトが入っていた。証言者も当然いる。
そもそも、殺害の様子から静眼の体力や力では無理な殺され方をされていた。
司法解剖の結果、被害者は全身をナイフのような鋭器で10箇所以上刺され、頭を数箇所殴られていた。ここまでやるには、相当の殺意と体力と時間がなければ不可能だ。
犯人は男か、異常なまでの殺意のある人間か。更なる捜査が求められた。
静眼はそんなわけでどう考えてもシロに限りなく近かったので、すぐに帰された。
勝也は、静眼を家まで送った。
「ありがとう。助かった。」家の前で静眼は言った。
「ううん。何か事件の事で何か思い出した事があったら、あの名刺の連絡先に連絡して。」
「うん。」
「あ。でも、それ以外の事で何か辛くなったり何か思い出して泣きそうになったら、この携帯の方に連絡して。」勝也は予め書いておいたアドレスのメモを手渡した。
「一応・・・。むごいもの、見ちゃったし・・・。」
「・・・ありがとう・・・。」静眼はじわっと目を潤わせた。
そのまま静眼は泣いた。
「恐かったよう。」ぽろぽろと、人前で我慢していた分が流れてきた。
「うん。」勝也は静眼を強く抱きしめた。
ジャケットの固い布地が、静眼を強く包む。
「ふ・・・うう・・・ぐ・・・」静眼は、しゃくり上げて泣いた。涼しげな、静かな夜だった。
星野は頭を悩ませた。
「武藤、お前、これどう思う。」星野は勝也に手渡した。
「何ですか?」勝也はのんびりとそれを受け取った。
「ダイイングメッセージは、この殺され方じゃ無理だろう。犯人の仕業と考えるのが理にかなってると思うが。」星野の目が光る。
・・・これは。
俺
と書いているように見える。確かに。
「写真で気づいたんだよ。現場では分からなかった。」
「・・・どういう事なんでしょう。」
「さあ。」
10箇所以上あった傷が、実は字を表していた。のだろうか。
全身を全体的に見ると明らかに『俺』と記されている。
・・・俺?
「サイコパスかもな。犯人は。あるいは愉快犯か。」星野の眉間に一層深く皺が寄る。「俺が一番嫌いなタイプの事件だ。」
普通の殺人ではない、殺人そのものを快楽としてやるような精神的に異常な犯罪者を指す。このような事件は稀だが、0ではない。勝也も経験は浅いが、2,3件当たったことがある。
「こういう奴らはゲームのように挑戦状みたいなものを出してくる。俺はそういう推理クイズみたいのが大嫌いなんだよ。どうか気のせいあってほしいよ。これ。」星野は溜め息をついた。めずらしく弱気だ。
「ううん・・・。」勝也は黙り込んでしまった。気のせいなのだろうか・・・。そうであってほしいが・・・。
被害者の見開かれた目が、勝也の額を見つめる。
静眼は、霊を信じない人だ。
昔から家は無宗教で、霊感も無くて、恐い話にも興味が無くて、とにかく普通の女の子だ。
「霊が見えるの。」「天使がいるわ。」そんな話を聞くと「ふうん。」と、ごくごく他人事のように捉えていた。否定も肯定もせず、ただふうん、と。
夜中、静眼は初めて幽霊のようなものを見た。事件から1週間弱経った夜だった。鈴虫の声がちょうど合う、涼しい風の吹く夜。
その殺された彼、に限りなく近い姿が、ぼうっと静眼に話しかける。「・・・助けて。助けて。」
静眼は恐くなって布団にもぐりこもうと思ったが、なんだか思っているより恐くなかった。しかも、いつも見ていた彼とは少し雰囲気が違って、少し優しさが強い感じだった。普段の彼はもっとスポーツマンでガツンと強い感じの人だった。
静眼は、首をかしげて彼を見つめた。
「あっ」すぐに彼はいなくなった。
「彼の別の彼が、彼を殺したの。」という言葉を最後に残して。
「・・・俺?」静眼は理解が出来なくて聞き返した。
「うん。これ、ほんとは人に言っちゃいけないけど、静眼ちゃんは特例。」勝也は星野と話した事を伝えてみた。何か静眼は知っているのでは、ととりあえず考えてみた。
「なんか思い当たる事ない?」
「・・・ううーん・・・。」
「・・・。」
「俺が、殺したって事かな。」
「え?」
「いや、あのね。私って別に幽霊とか信じないんだけどさ・・・。」最近起こった事を、静眼も打ち明けた。
「彼の別の彼が彼を殺した?」
「なんかめちゃくちゃでしょ?私、何がなんだか・・・。」
「ゲシュタルトみたいだね。」
「げしゅ・・・?」
「心理セラピーで、同じ言葉を何度も繰り返して治療する方法があるんだよ。」勝也は大学時代に書いた卒論を思い出した。人文科学を専攻していた彼は、ゲシュタルト療法とブリーフセラピーについて書いたのだ。星野の苦手なサイコパス系の事件がなんとか解決したのも、勝也の心理学の知恵あってこそだった。
「彼の別の彼か・・・。」勝也はぼんやり考えた。
「どう別なんだろう。」ほんのりと疑問が沸く。
「さあ・・・。」静眼はまさにちんぷんかんぷんである。
公園のベンチに2人並んで座っている。
時はぽかぽかした陽の優しさでゆったりと流れていった。どんよりとした思考が上を雲のように通っていく。
彼岸花が、ゆさゆさと風に揺られていた。
真っ赤な色が、鮮やかに目を刺激した。
(続)
この記事を書いた人
- コミュニケーションハッカー。新時代のゲームPHEAlosophy(フィーロソフィー)研究所、AkibaColoursで『日本のサブカルチャーが人の心に与える影響』について日々研究している。あらゆる心理セラピー、自己啓発、コーチングに静かなる反旗を翻す『カラーチャット』というゲームの提供も行っている。普段は秋葉原の神田明神すぐ裏でひっそりと暮らしている。HP→http://akibacolours.main.jp
この投稿者の最近の記事
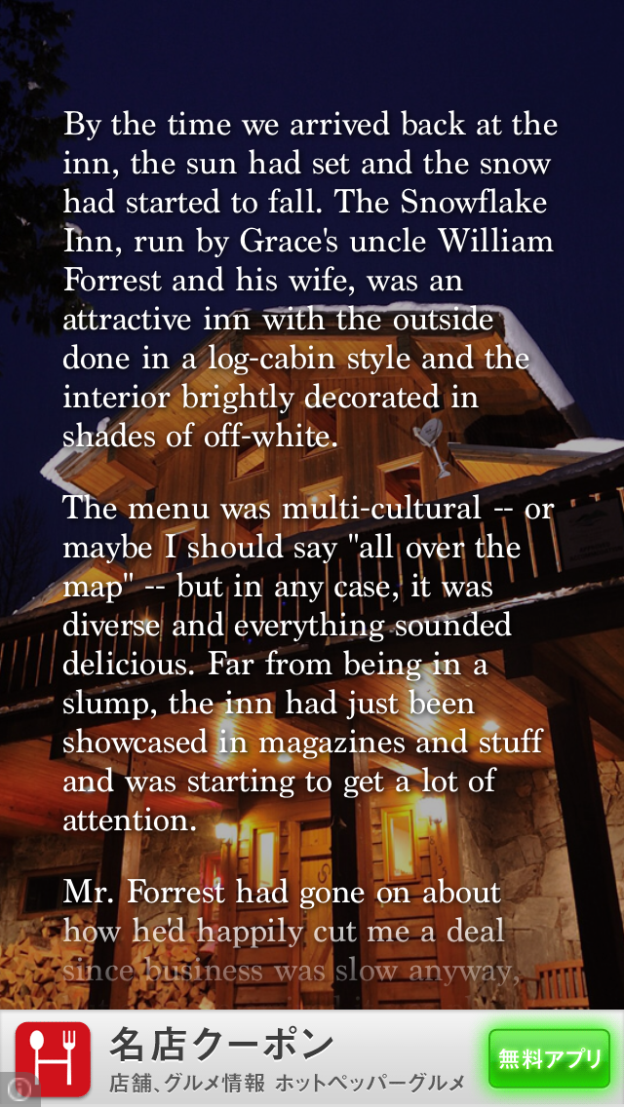 AkibaColours2014年2月24日サウンドノベルは世界に通用するか? 『かまいたちの夜』英語版を徹底検証
AkibaColours2014年2月24日サウンドノベルは世界に通用するか? 『かまいたちの夜』英語版を徹底検証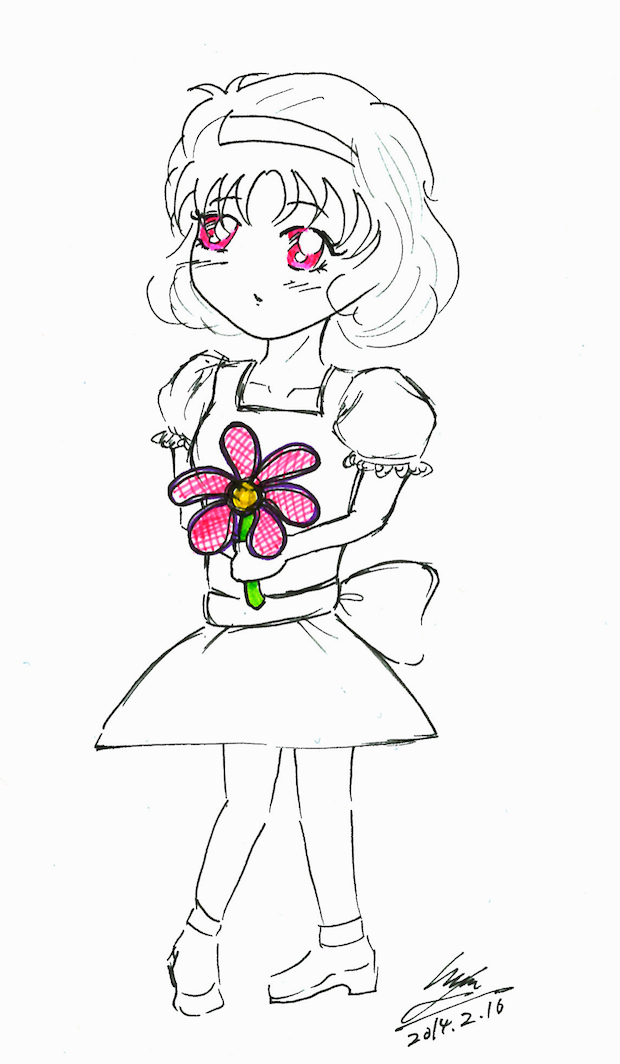 エッセイ2014年2月17日コミュニケーションハッカー 〜救命チャット24時〜:Case1 お金の問題は心の問題?
エッセイ2014年2月17日コミュニケーションハッカー 〜救命チャット24時〜:Case1 お金の問題は心の問題?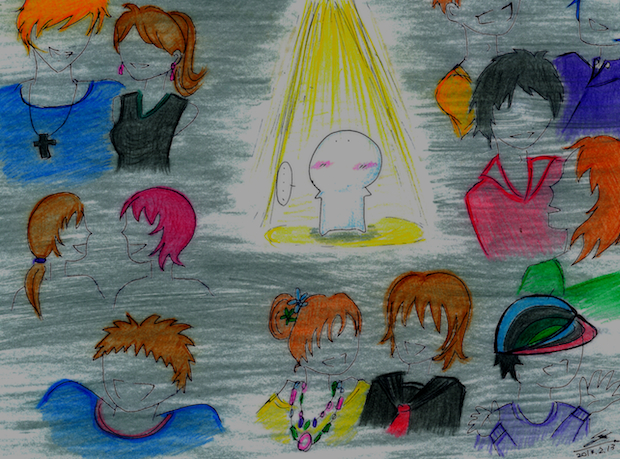 AkibaColours2014年2月13日ヲターヘル・アナトミア(2)…社会も他人も関係ない。あなたはあなた。
AkibaColours2014年2月13日ヲターヘル・アナトミア(2)…社会も他人も関係ない。あなたはあなた。 AkibaColours2014年2月12日【小説】殺害パラドックス 第2話
AkibaColours2014年2月12日【小説】殺害パラドックス 第2話